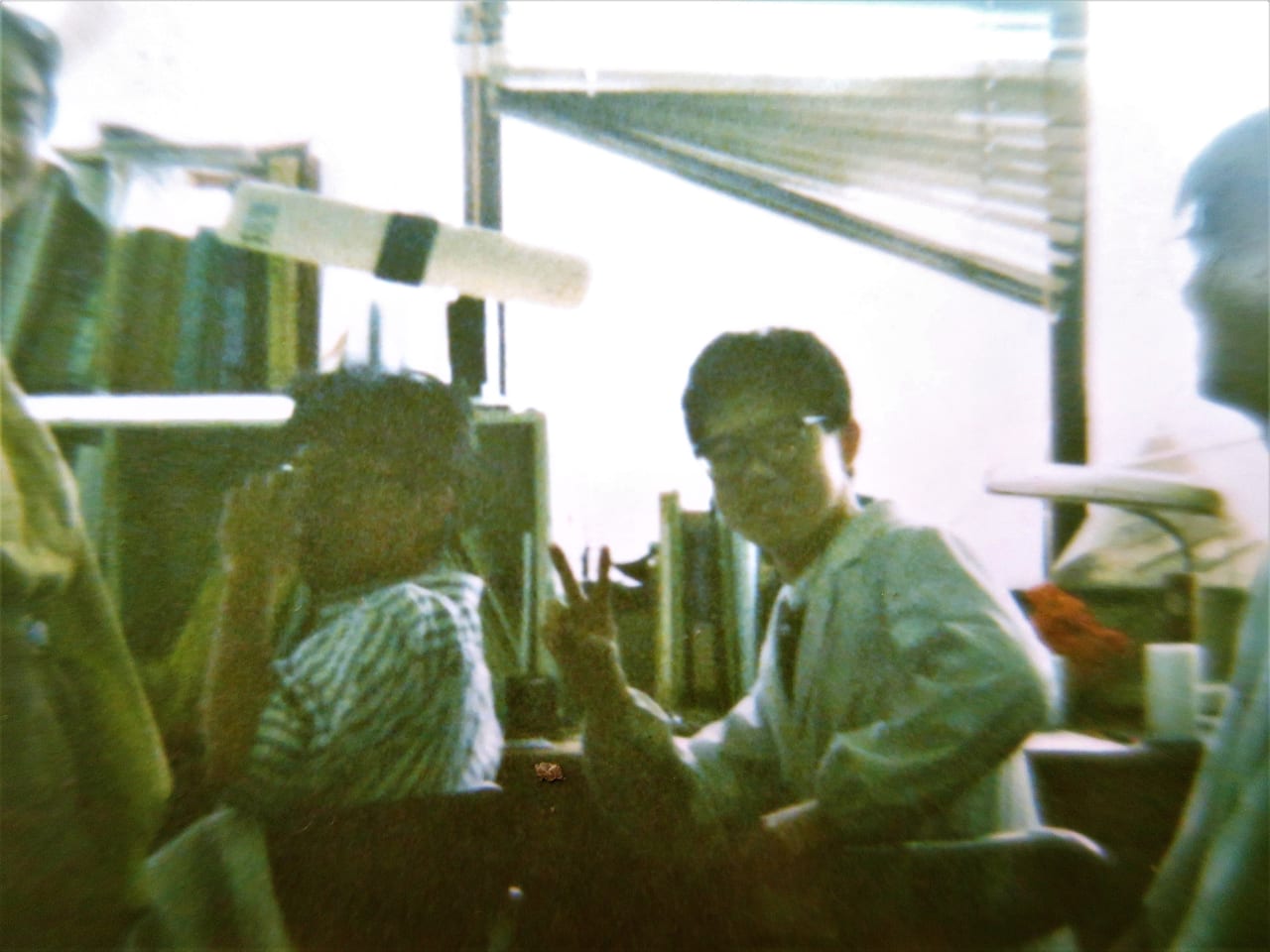 薬学部時代の筆者 修正
薬学部時代の筆者 修正大学4年生の僕は有機化学合成、いわゆるケミカルの研究室に属し、合成薬の副作用を防止する研究を行っていた。このまま大学院に進学し2年後に一流製薬企業への就職が、ほとんどの東北大学薬学部生にとっての既定路線だった。
しかし……大切な何かをやり残したまま進んでしまうという漠然とした不安に包まれていた。そうして卒業後の進路について真剣に悩みはじめた4年生の夏、僕は薬学部の裏に広がる薬用植物園を散歩するようになっていた。けっして薬草に興味があったわけではなく、ただ散歩する場所を求めていただけであることを、当時の僕ならばムキになって強調したであろうし、事実、興味はなかった。それほどに「薬草に興味がある」学生は薬学部内で異端視される雰囲気が漂っていた。有機化学合成がエリート路線であり「文明」の象徴に対して、薬草は時代遅れで、よくいえば「過去の文化」であると認識されていたからである。
だからこそ、そんな薬学生が珍しかったのだろう、薬草園を整備している地元のおっちゃんたちが「よう、兄ちゃん!○☓△……」と声をかけてくれるようになり、当初は戸惑いつつ微妙な笑顔だけで応えていた。なにしろ仙台に住んで3年半になるにも関わらず東北弁がほとんど聞き取れないし、そういえばこうして地元の人たちと触れあった記憶が無い。近代的な研究棟から目と鼻の先にある素朴な作業小屋は僕にとって異世界であり、作業服のおっちゃんたちはまるで外国人だった。(失礼ながら)率直に表現するとたいへん「粗野」な人たち。それでも(失礼ながら)怖いもの見たさのように足が向くのだから不思議なものである。きっと無意識のうちにそこに「大切ななにか」を感じとっていたのではないだろうか。そして、おっちゃんたちはいつも「よう!☆■÷……」と向こうから踏み込んできてくれ、気がつけば夜、作業小屋で辰吉丈一郎のボクシング世界タイトルマッチを視ながら盛り上がっていたこともある。
昭和31年に制定された法律(大学設置基準/文部省令第28号)によって薬学部は一定面積以上の薬用植物園の所有を義務づけられ、なかでも東北大学薬学部は青葉山に位置している好条件を活かして、広大で多種にわたる薬草園を所有している。しかし宝の持ち腐れとはこのことで、大学3年時に薬草学の授業があるにはあったが薬草園でおしゃべりしながら下手なスケッチをし、一夜漬けの試験勉強で単位が取得できてしまう程度で、指導する教授も指導される学生も力はまったく入っていなかった。ちなみに医学部にいたっては薬草の授業がまったく存在せず、「薬草に興味がある」医学部生が異端視される傾向は薬学部以上に強く、いまもその雰囲気は根強い。つまり日本には薬草の専門家を育てる組織は存在しないのである。では、いったいいつから医薬学部は薬草を軽視するようになったのだろうか。
 森のくすり塾 薬草園
森のくすり塾 薬草園戦前戦後、日本の薬学者は薬草に含まれる成分を分析し、その構造を解明し、さらには植物の中でどのような過程を経て生成されるかを解明することに精力を注ぎ、その分野では驚くほどの発展を遂げた。薬用植物園の法律が制定された1956年ころは、そんな発展の時代の最中だった。しかしおおかたの薬草が調べ尽くされ、薬草から新薬を発見する可能性が低くなるとともに薬草の地位は低下していった。昭和30年代以降、高度経済成長によって薬草を含めた里山への意識が離れていったという国民全体の雰囲気もあったであろう。そして薬草園のおっちゃんたちは薬学生にとって遠い存在になっていった。
いっぽうメンツィカン(チベットの医学大学)はまさに薬草専門家の養成機関であり、チベット社会において薬草の地位は保たれている。ヒマラヤ薬草採集では製薬工場のおっちゃんたちと医学生が一緒になって働くのだが、あきらかにおっちゃんたちのほうが採取能力に優れていた。製薬工場の中でも遊牧民出身の人たちが選ばれてきているのだから敵うわけがない。チベット語でおっちゃんのことを「アクー(↗ 語尾を上げる)」と呼ぶ。そして、アク・シャンバをはじめとして、僕たち医学生はアクーたちを尊敬していた。でもチベットの子どもから「ジョジョー(お兄さん)」ではなく「アクー」と呼ばれたとき、ちょっと複雑な気持ちになり、すっかり薄くなった髪の毛を顧みたものだった。
そういえばあのときの薬草園のおっちゃんたちの歳に近づいてきている。今度は僕が薬草園のおっちゃんとして、若者たちに「よう!」と声をかける役目が廻ってきたようだ。
 メンツィカン学生時代 左端は筆者 2001年
メンツィカン学生時代 左端は筆者 2001年 製薬工場のおっちゃんたち
製薬工場のおっちゃんたち参考リンク:東北大学薬用植物園